自分と仲間を守るためハラスメントについて学ぼう
講演
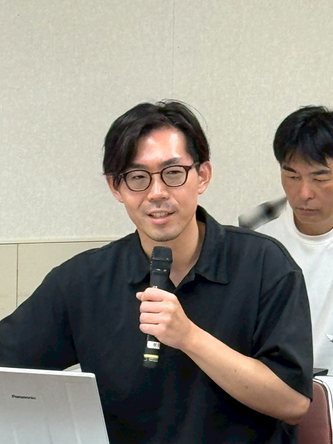
小貫書記次長
8月3日(日) 第21回労働安全衛生学習交流集会を開催し、7組織45名(うちzoom20名)が参加しました。
記念講演では埼玉医労連・小貫書記次長を講師にハラスメントについて学びました。
講演の概要
言われて嫌だと感じたこと=即パワハラではない。
①優越的な関係を背景とした言動か?
②業務上必要かつ相当な範囲を超えているか?
③就業関係が害されているか?
この3要素すべて満たすかどうかを客観的に判断する。命に関わる重大な問題行動への一定程度の強い注意は該当しない。
一番多いのはパワハラ
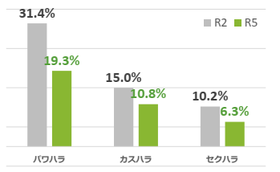
パワハラの相談先として組合の出番
◆ハラスメントかな?と思ったら
①記録する(いつどこで誰から何を言われた、された)
②相談する(1人で抱え込まないことが重要、相談する中で考えが整理される)
◆同僚が被害を受けてるのを見たら(傍観者にならない)
①声をかける(心配してると伝える)、
②話を聞く(否定しない)、
③相談先を伝える(労働組合の出番)
◆組合としてヒアリングするポイント ※ハラスメントかどうかを判断する場所ではない
・いつどこで誰からどうされたのか、今どういう感情で、仕事に行けているのかどうか、を聞く。
・聞いた内容を書き出し要求書を出す それが事実だったか事実確認させて回答させる
→事実なら謝罪や指導させることを求める、と2段階で。
グループ討論
講演の中で、具体的な事例をもとに「これはパワハラに該当するか?」とグループで話し合い、意見を出しあいました。
講演後にはグループで感想交流を行い、「何がハラスメントに該当するかわかりやすかった」「裏付けとしての知識を持った上で客観的にヒアリングし、組合として要求していけるといい」と感想が出されました。
